こんにちは、クロスシー編集部です。
MCN(マルチチャンネルネットワーク)が中国でも存在感を高めています。MCNの発展には、ネット上のコンテンツプラットフォームの増加や、そこにおけるインフルエンサーの人気の拡大が関係しています。
2015年からネットにオリジナルの動画を公開しているpapiちゃん(中文:papi酱、酱はジャンの音で「ちゃん」を表す)はワンホンの草分け的存在であり、現在「papitube」というMCNの組織を運営しています。
本編では前半でpapiちゃんを主軸に、中国の動画で人気のカテゴリ「搞笑」について紹介し、後半で中国でのMCNの現状を解説します。
※ワンホン…中国語でネットの有名人の意味で、インフルエンサーを意味する。
▼中国におけるKOLマーケティングの存在感とは?
【中国SNS】フォロワー数水増し事件発覚で注目度高まる「真実のフォロワー数計測ツール」/それでも企業がインフルエンサー(KOL)を重宝するワ
こんにちは、クロスシー編集部です。本日は中国向けのマーケティング施策に欠かせないインフルエンサー「KOL(Key Opinion Leader)」の起用について、その選出から効果測定までの現状の課題と打開策についてご紹介します。目次KOLとは? 中国のインフルエンサーマーケティングの落とし穴とは!? フォロワー水増し事件がつきつけた課題それでもKOLの存在意義は大きく…旅行系KOLでは実際に来店増加の事例も「ゾンビフォロワー」「サクラ」を排除し、KOLの真の実力をはかる「Miaozhen」...
【訪日ラボは、インバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2025」を8月5日に開催します】
2016年に大ブレイクし約2億円の融資を受けたpapiちゃん、ハチャメチャなようで完成度の高いコンテンツが人気に火をつける
中国のワンホンといえばこの人とも言われるpapiちゃんは、本名を姜逸磊(JIANG Yilei)といいます。上海出身の87年生まれで、2016年に中央戯劇学院の大学院を卒業しました。在学中の2015年に、ネット上でオリジナルのムービーの公開を開始しており、2016年の2月にネット上にアップした「男性生存の法則」をはじめとする複数の作品が注目を集めました。結果としてこの年、1200万元(現在のレートで約2億400万元)の融資を獲得します。
この作品は交際中の男性への女性の理不尽なまでの要求はじめ、女性の心理を解説したものです。動画にはpapiちゃん自身が複数の髪型、衣装で登場します。シンプルな構図と、まくしたてるような口調が特徴です。加工して高速再生される口調で語られるその心は、聞いた瞬間は理屈があるようにも感じられるものの、次の瞬間にはロジックにほころびがあるようにも思えてきます。しかし、深く考える間もなく次の言葉が投げかけられます。

この動画は現在も動画配信サイトである「iQiyi」や「ビリビリ」で鑑賞することができます。冷静に咀嚼してみると単なる屁理屈も混ざっているものの、彼女の語り口に圧倒されているうちになんだか正しいことを言われているような気分にまでなってくる、そんな面白さが存在しています。
こういった動画は彼女の同年代の関心を集め、人気の作品では視聴回数で数億回を記録するものも少なくありません。papiちゃんのWeiboは現在2871万フォロワー、バイドゥ傘下の動画配信サイトiQiyiには78.5万人のチャンネル登録があります(2018年9月24日現在)
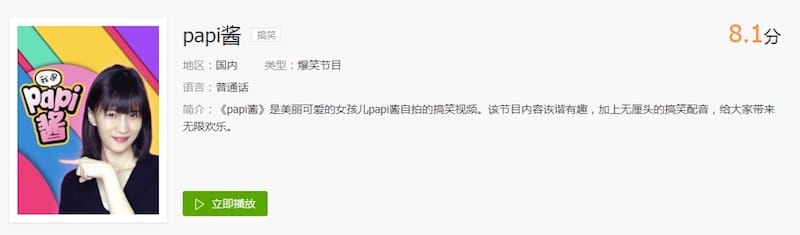
また大学院の卒業翌年にあたる2017年には、中国インターネット広報大使として、WWFの中国における広報大使の任命を受けており、世界的にもその影響力の大きさを認められています。
中国のUGC/PUGC/PGCにおいては、彼女の作品のようにくだらない話題についてシリアスな口調で掘り下げる作品を「搞笑」というカテゴリとして扱い、現在も非常に人気となっています。
90後(90年代生まれ)のKOL「办公室小野」は会社のデスクで料理をするというハチャメチャな場面設定でありながら、その料理の完成度の高さでファンをつかんでいるようです。一見不条理なことをしているようで、同時にどこかに真理を持つストーリーが人気をつかむ秘訣と言えそうです。
※UGC(User Generated Content)=ユーザーによりつくられたコンテンツ
※PUGC(Professional User Generated Content)=完成度の高さや構成で大衆の目を引くコンテンツありながら(Professional)、その投稿者のキャラクターは一般人程度の特徴に抑えられており(User)、結果として視聴者から親近感が抱かれやすいという特徴がある。
マルチチャンネルネットワーク(MCN)のpapitubeはクリエイターの質とその布陣に強み
MCN(マルチチャンネルネットワーク)とは、YouTubeなど動画配信サービスが台頭し始めた2000年代に登場した概念です。SNSや動画配信プラットフォームにおいてコンテンツを投稿するユーザーの、コンテンツ制作や配信をサポートを指します。あるウェブニュースによれば、中国におけるMCNは、2017年ごろよりショートムービーの人気の高まりに合わせて出現したと言います。
これによれば、2016年以降、中国のコンテンツマーケティングでは「PGC(※)の制作」がプロモーションを成功させるための合言葉のようになっていました。ところが昨年の秋ごろから、PGCといった言葉がだんだん聞かれなくなり、代わりに「契約クリエイターの多いMCN」が広告主に対して重要な口説き文句となってきたのです。
※PGC(Professionaly Generated Contents)=映像の専門家が参与し完成したコンテンツ
現在中国のインターネット上で、個人や一組織によるSNSや動画配信サイトのアカウント運営を通じて、世間に存在感を打ち出すことはもはや現実的ではありません。運よく存在感を打ち出したとしても、非常にたくさんのSNSプラットフォーム、動画配信プラットフォームが存在する中国で、コンテンツ発信を継続的に収益化するのは難しいと言えるでしょう。
こういった状況を受け、コンテンツの制作、発信への協力はもちろんのこと、コンテンツの拡散や、広告出稿やその他収益化を図るための営業活動を組織として行うのがMCN企業です。実際、中国のKOLランキングにおいて上位にランクインする人物は、全員どこかしらのMCNに所属をしています。
前述のpapiちゃん(姜逸磊)は、こういった流れに一足早くキャッチアップし、2016年の時点で共同事業運営者の楊銘氏とともにMCNプラットフォーム「papitube」を立ち上げました。中国版TwitterであるWeiboはじめ、bilibili動画やショートムービーのプラットフォームなど複数のサービスで活動するインフルエンサー(ワンホン、KOL)をマネジメントしています。
papitube は2018年4月で設立2周年を迎えており、6月の時点では約60名のクリエイターが所属していると発表されています。papiちゃんは2周年記念のパーティにおいて、今後クリエイター数を100名まで伸ばすことを語りました。

MCNの実力を左右するのはクリエイターの質とその布陣ですが、中には単なるPGC制作者の寄せ集めとなっている団体もあるといいます。
papitube傘下のクリエイターは、ワンホンの中のワンホン、コンテンツ制作で中国一ともいえるpapiちゃんの眼鏡にかなったクリエイターであり、その実力は疑う余地はありません。加えて、papitubeの最も大きな特徴は、クリエイターの得意とする内容が非常に広範にわたることにあります。現在中国で最も実力のあるMCN組織の一つであるといえるでしょう。
まとめ ~今後コンテンツマーケティングのカギを握るのはMCN、papitubeには要注目~
一世を風靡した彼女のニュースはあまりに衝撃的だったため、まるで彼女を過去の人物のようにとらえてしまう人も今ではいます。papiちゃんの動画作品において、初めて出稿された広告には2200万元(3億7000万円)という価格がついたと言われています。
ところが実際は、前半で紹介したSNS、動画配信チャンネルの登録数が示すように、その影響力はまだまだ絶大です。Bilibiliでは200万、300万の再生回数を記録することは珍しくなく、合計再生回数は2.4億回を超えており、なによりもそのクリックレートは依然として高いのです。
そんな彼女が今、時勢を読んで手掛けるMCN事業。今後papitube所属のクリエイターが市場の注目を集め、新たな方向に成長していくことも考えられます。中国のMCNの動きを注視していく中でも、特に注目すべき組織です。
<参考>
【7/3開催】宿泊のイマを考える「ホスピタリティサミット」

インバウンド需要の高まりに加えて2025年は大阪・関西万博の開催など、国内旅行者に限らず訪日観光客の増加も加速する日本。今、国内観光の需要は増加する傾向であり、ホテル・宿泊業界は大きなビジネスチャンスの時代を迎えています。このような状況において、宿泊施設としての取り組みやサービスの品質改善は、お客様に選ばれ続けるための最重要課題となっています。
本イベントでは「顧客への情報アピール」「顧客体験(ゲストエクスペリエンス)」「運営のデジタル化」など、施設運営に必要なをテーマを、市場の最前線を走るエキスパートたちが集結。お客様が施設を見つける「旅マエ」から、実際に滞在する「旅ナカ」まで、あらゆるフェーズにおける最新戦略と成功事例を徹底解説します。
<本セミナーのポイント>
- 変わりゆく市場の状況と、今後注目のトレンドを把握できる
- 旅マエの顧客行動を理解し、集客・予約率アップのヒントが得られる
- 旅ナカの接客品質を高め、顧客満足度向上に繋がる実践的な対応を学べる
- 各分野の専門家から、ビジネスを加速させる具体的な戦略や成功事例が聞ける
詳しくはこちらをご覧ください。
→宿泊のイマを考える「ホスピタリティサミット」【7/3開催】
【8/5開催】「THE INBOUND DAY 2025 -まだ見ぬポテンシャルへ-」

2025年、日本のインバウンド市場は訪日外客数が過去最高の4,020万人に達するとの予測や大阪・関西万博、IR誘致などによる世界からの注目度の高まりから、新たな変革期を迎えています。一方で、コロナ禍を経た現在、市場環境や事業者ごとの課題感、戦略の立て方は大きく様変わりしました。
「THE INBOUND DAY 2025」は、この歴史的な転換点において、インバウンド事業に携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、日本が持つ「まだ見ぬポテンシャル」を最大限に引き出すための新たな視点や戦略的アプローチを探求、議論する場です。
初開催となる今回のテーマは「インバウンドとは」。
参加者一人ひとりが、「自分にとって、企業にとって、地域にとってのインバウンドとは何か」「いま、どう向き合うべきか」「どうすれば日本の可能性を最大化できるのか」という問いを持ち帰り、主体的なアクションへとつなげていただきたいと考えています。
<こんな方におすすめ>
- インバウンド戦略の策定・実行に課題を感じている経営者・担当者
- 最新の市場動向や成功事例を把握し、事業成長に繋げたい方
- 業界のキーパーソンと繋がり、新たなビジネスチャンスを模索したい方
- 小売・飲食・宿泊・メーカー・地方自治体・DMO・観光/アクティビティ事業者
- インバウンド関連サービス事業者、およびインバウンド業界に興味がある学生
→「THE INBOUND DAY 2025」特設ページを見てみる
【インバウンド情報まとめ 2025年6月後編】「2030年6,000万人・15兆円」の目標達成に向けた議論 ほか

訪日ラボを運営する株式会社movでは、観光業界やインバウンドの動向をまとめたレポート【インバウンド情報まとめ】を毎月2回発行しています。
この記事では、主に6月後半のインバウンド最新ニュースを厳選してお届けします。最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください。
※本レポートの内容は、原則当時の情報です。最新情報とは異なる場合もございますので、ご了承ください。
※口コミアカデミーにご登録いただくと、レポートの全容を無料にてご覧いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「2030年6,000万人・15兆円」の目標達成に向けた議論 ほか:インバウンド情報まとめ 【2025年6月後編】
今こそインバウンドを基礎から学び直す!ここでしか読めない「インバウンドの教科書」

スマホ最適化で、通勤途中や仕込みの合間など、いつでもどこでも完全無料で学べるオンラインスクール「口コミアカデミー」では、訪日ラボがまとめた「インバウンドの教科書」を公開しています。
「インバウンドの教科書」では、国別・都道府県別のデータや、インバウンドの基礎を学びなおせる充実のカリキュラムを用意しています!その他、インバウンド対策で欠かせない中国最大の口コミサイト「大衆点評」の徹底解説や、近年注目をあつめる「Google Map」を活用した集客方法など専門家の監修つきの信頼性の高い役立つコンテンツが盛りだくさん!










