「2020年までに全世界の店舗で使い捨てストローを廃止」というスターバックスの声明が2018年6月に発表されました。なぜ今、小さなプラスチック片であるストローが取り立ててそれほど大きな批判を呼ぶのか、よくわからないと感じている人も多いのではないでしょうか。
欧米のストロー禁止(plastic straw ban)運動は、実は日本のインバウンド業界として汲み取るべき強い食へのメッセージを含んでいます。ストロー禁止問題は日本のインバウンド業界にとって、どのような意味を持つのかまとめました。
泊食分離とは │ 意味・効果・観光庁による推進・現場の実情
観光庁は、さまざまな日本食を楽しみたい訪日外国人のニーズに応えるべく、旅館以外で食事をとる「泊食分離」を推進しています。しかし観光庁の方針とは裏腹に、現場レベルでは実施率や実施意欲が停滞しています。この記事では、「泊食分離」の意味・効果・観光庁による推進・現場の実情について詳しく見ていきます。目次「泊食分離」とは:名前の通り“宿泊”と”食事”を分けることなぜ観光庁は「泊食分離」を推進する?:訪日外国人のニーズが背景に訪日外国人は日本滞在中に様々な日本食を楽しみたい「泊食分離」で期待される効...
インバウンド受け入れ環境整備を資料で詳しくみてみる
- 「翻訳・多言語化」を資料で詳しくみてみる
- 「多言語サイト制作」を資料で詳しくみてみる
- 「多言語化表示サービス」を資料で詳しくみてみる
- 「テレビ電話型通訳サービス」を資料で詳しくみてみる
- 「訪日外国人向け道案内」を資料で詳しくみてみる
ストロー禁止騒動のあらまし
プラスチックのゴミは以前より世界的な問題になってきました。特に近年、この中でも海洋廃棄が問題視されています。
プラスチックは自然に分解されることが難しいため「焼却・埋め立て・海洋廃棄」のいずれかが最終処分になります。海洋廃棄されたプラスチックのゴミは海に漂い、クジラやカメなどの海洋生物が餌のクラゲと間違えて、食べてしまうケースが多発しているためです。
こうした環境問題を受けてアメリカで始まった「ストロー禁止」運動は3つの象徴的な事例と共に語られることが多いようです。
- スターバックスによる2020年使い捨てストロー全廃の声明発表
- スターバックスのお膝元・シアトルにおけるプラスチック製ストロー禁止条例施行
- フットボール界のスター・トム・ブレイディ氏によるアンチ・ストロー・キャンペーン
この中でも日本のメディアでよく目にするのはスターバックスによる2020年までにストロー全廃宣言です。
よく見ると穏当なスターバックスによる「ストロー廃止」宣言。メディアがセンセーショナルに取り上げる理由とは?
実際にスターバックスのプレスリリースを見てみると、その内容は極めて穏当なものであることがわかります。
「ストローがなくても飲みやすい蓋(リサイクル可能なプラスチック)を用意し、プラスチックではない代替材によるストローを用意します。巨額の予算を投じてリサイクル可能・自然分解で堆肥化されるカップの開発に乗り出します」
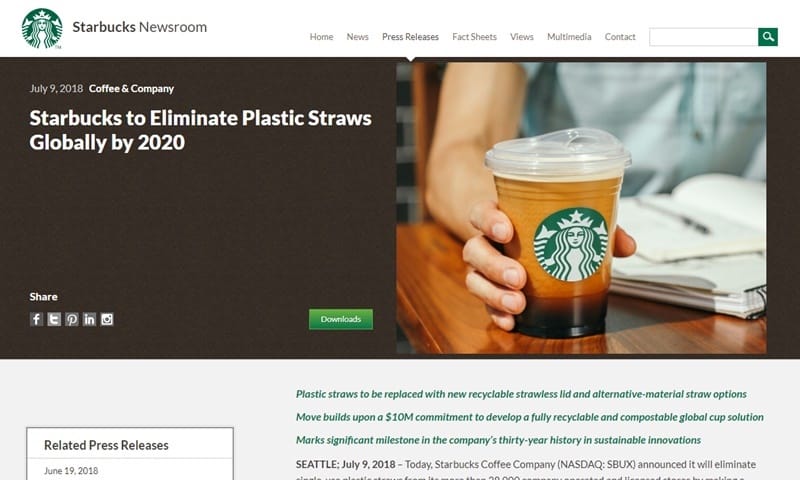
環境問題におけるゴミ対策の3原則は「REDUCE-REUSE-RECYCLE(減らす・再利用する・リサイクルする)」です。
じつはスターバックスはストローだけでなく、プラスチック製品全体を見直してこの3原則を行うとしています。メディアにおいてストローだけがことさら取り上げられるのはナゼでしょうか?
「カフェでくつろぐ」という日常の楽しみに潜む原罪を問う・メッセージ性の強い「ストロー禁止」
ストロー禁止は象徴的なメッセージを私たちに伝えています。
誰もがちょっとした日常の楽しみで何気なく使い捨てしているストローと海洋生物がプラスチック汚染で苦しんでいるという2つの対極事例を結びつけ、一般人の当事者意識を目覚めさせるという狙いです。
カフェで冷たいドリンクを片手にスマホチェック、好きな音楽でしばしくつろぐ…誰もが経験のある日常の小さな楽しみが地球の環境を破壊していると知れば、それを続けることは居心地が悪いに違いありません。
プラスチック製ストロー禁止条例施行をしたシアトルはスターバックスやマイクロソフトといった企業城下町で富裕層が多い・意識が高い街です。またトム・ブレイディ氏はフットボール界のスターで、超有名モデルの夫で、誰もが憧れるセレブです。
注目度も高く、オピニオンリーダーである街・人物・企業が揃って取り組んでいる「ストロー禁止」の流れは、今後も注目され、世界的な共感を得ていくのかも知れません。
「食べることは選択である」という訪日外国人は多い。まだまだ対応しきれていない日本のインバウンド業界
今回のストロー禁止に見られるように、海外では食とライフスタイルは切っても切れない関係にあります。自分が食べるものを自分で選択するという考え方は日本で考える以上に強いのです。
この続きから読める内容
- 飲食店でのインバウンド対策で必須知識!訪日外国人に多い「ベジタリアン」とは?
- 日本のインバウンド業界でもそろそろ「食に対する選択と決定」を尊重しないといけないのでは?
- Trip AdvisorのTOKYO100で3位入賞「割烹伊勢すえよし」の実践するインバウンド対策とは?
- まとめ:訪日外国人への「食のおもてなし」は美食だけではない。インバウンド業界は「食の選択」を用意するべき
- 飲食店のための宗教別インバウンド対策・おもてなしポイント:仏教編
訪日ラボ無料会員
登録すると…

50,000ページ以上の
会員限定コンテンツが
読み放題

400時間以上の
セミナー動画が
見放題

200レッスン以上の
インバウンド対策の
教科書が学び放題
\無料・1分で登録完了/
今すぐ会員登録する









